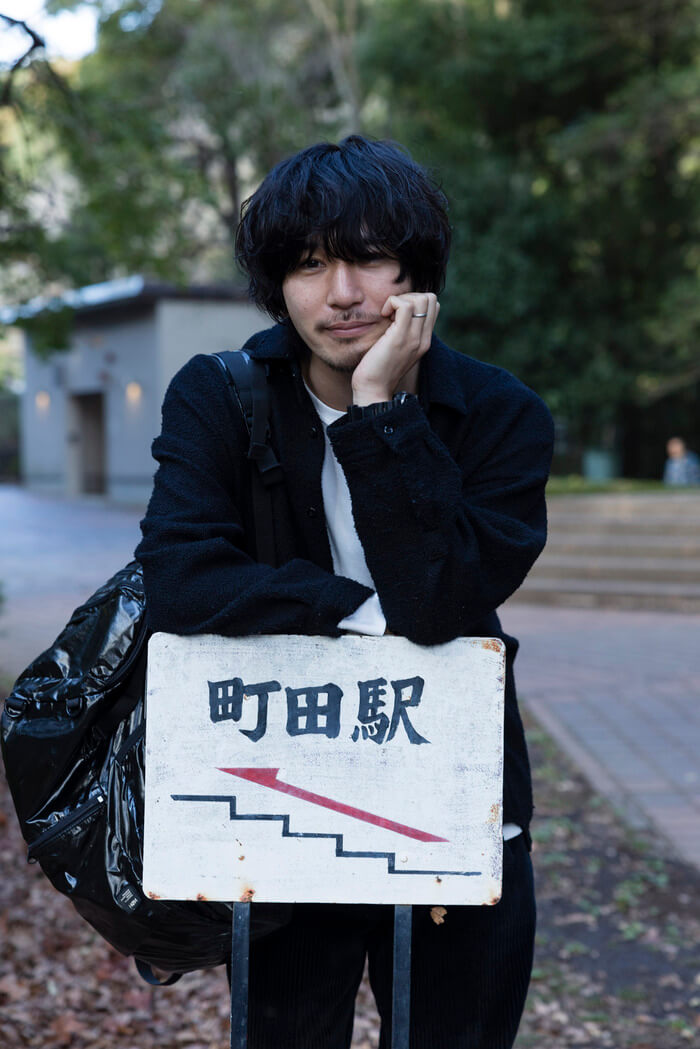町田に住んでいた頃から、
小説家としての僕と今のくらし
更新日:2024.03.21

カツセマサヒコさん 小説家
現在は小説家として大活躍しているカツセさん。以前は町田市に住んでいたこともあり、当サイトにもショートストーリーを寄稿するなど、縁のある作家さんです。在住時によく訪れていた場所をめぐりながら、当時の思い出や、小説家としての今の生活、お仕事観などたっぷりと語っていただきました。
自分が子ども時代に訪れていた町で、
子育てが始まった

――町田に住んでいたのは、いつ頃でしょうか?
2014年から2020年までの約6年間です。27歳の頃に編集プロダクションに転職して勤務地が下北沢になったので、そのタイミングで小田急線で一本で通える町田駅へ引っ越しました。編集プロダクションも3年で辞めて独立しましたが、その時期に子育てが始まったこともあり、環境が良かったので変わらず町田に住んでいました。
――子育ての時期と、町田に住んでいた時期がリンクしてるんですね。
子どもが小さかったときは、遊びに行く先は大体、シバヒロか芹ヶ谷公園の2択でした。自転車の後ろに子どもを乗せて芹ヶ谷公園の脇の急な坂道を一気に登るときに、ずっと子どもが“頑張れ、頑張れ”と歌うように叫び続けていたんです。それがいまだに本人に影響を与えているみたいで、今でも何かあると“頑張れ、頑張れ”と歌うように騒ぎ出します。本人はもうほとんど覚えていないはずですけど、坂道で必死に応援してたっていう記憶だけは、断片的に残っているのかもしれません。そういったことから、町田は親になってからのまちとしての印象が割と強いです。
ただ、このまちは祖父と祖母が住んでいた場所でもあります。 “町田のおばあちゃんちに行くよ”と言われて何度も連れて行ってもらっていたので、まち自体の賑やかなイメージや、そのまちに住むイメージは幼い頃から持てていたのかもしれません。以前、町田市民文学館「ことばらんど」の企画でイベントに登壇させていただいたときには、イベント会場と祖父の家だった住宅がかなり近所にあることを母から教えられて、少し散歩をしてみたりもしました。面影のある建物に出会したときは驚きましたし、人生の中で何度も関わっているまちなのだと再認識しました。

――小さい頃は、町田はどういうイメージでしたか?
まだ地元の駅に自動改札機がなく、駅員さんが切符をパチパチと切っていた時代だと思います。その頃から町田には自動改札機があったし、駅前はとても栄えていて、ゴミゴミしていました。今、ユニクロが入っているビルは昔、東急ハンズが入っていて、確か屋上に園芸やペットショップコーナーがあって、そこによく連れていってもらっていました。同じビルの2階にある遊具のある広場でも遊ばせてもらっていましたし、 “ジョルナ”にもよく通っていました。細かな記憶ばかりですけど、町田はそうやって何かを語らせるまちだと思います。
――久々に町田に来てみて、どんな印象ですか?
芹が谷公園まで足を延ばすことはほとんどないので、懐かしいです。この公園付近での出来事でよく覚えているのが、地域の餅つき大会にまぜてもらえたこと。子どもが保育園の餅つき大会の日に発熱してしまい、園を休むことになって、悔しがっていたんですけど、後日、たまたまこの辺りを歩いていたら、地域の方たちが餅つき大会やっていたんです。子どもが興味深げにその様子を見ていたら、どうぞどうぞ、とまぜてもらえて。地域の人たちの優しさに触れた日でした。


小説もエンタメのひとつ
ネトフリと同じ感覚で楽しんでもらいたい
――ちなみにご自身で読書はどれくらいしますか?
最近は平均週1冊、多くても週に3冊程度でしょうか。仕事で読まなきゃいけないときもありますし、執筆の兼ね合いで全く読まなくなる時期もあります。頻度もジャンルもバラバラですが、好んで読むことが多いのは、日本の現代小説でしょうか。人文系をパラパラと読むこともあります。
――小さい時から読書は、好きだったんですか?
小学生のとき、村山由佳先生の『おいしいコーヒーのいれ方』シリーズ(*1)や、宗田理先生の『ぼくらシリーズ』(*2)をよく読んでいました。そういう本ばかり読んでたから、大人には反抗した方がいいと思うようになったというか(笑)。生意気な学生でした。
ただ、本に救われたとか、そういう感覚は全くないです。本を読むとクラスの流行についていけなくて孤独になっちゃうとか、そういう恐怖心すらあったので、中学生になって通学時間が長くなったときに初めて自分から手に取るようになったくらいでした。だから本に救われた人生とは思わないし、自分の本に関しても、誰かの人生を左右したいといった気持ちは全くないです。
Netflixとかと同じで、本も娯楽のひとつでいい。その代わり、文字ならではの良さは絶対にあるのでその魅力をしっかり届けられればいいなと思っています。
――ライターと小説家だと、同じ書く仕事でも大きく違いますが、どちらかというと小説家タイプだったのでしょうか?
どちらも、とにかく大変です……(笑)。ただ、ライターは黒子に徹することもできますが、小説家は自分がフロントに立たなければならない人気商売なので、忘れられたらどうしよう、飽きられたらどうしよう、という不安が付き纏います。それがずっと心配で、大変な自転車操業が始まってしまったなあと時折思います。
――やっぱりずっと書き続けないと、不安なものですか?
ほかの作家さんの新作が面白かったり、別の作家さんが賞を受賞したと聞いたりすると、お腹が痛くなります(笑)。ただ、ちょうどこの前も、自分の連載のお仕事が一気に終わるタイミングがあったんです。家計にも響きますし、たしかに不安はよぎるのですが、 “これは脱皮したばかりでしばらく体が弱い時期にあるだけで、きっと今より強く大きくなるから大丈夫”と言い聞かせるようにして、休むことも大切にしています。

――町田市内でよく行っていた場所、として宮越屋珈琲もあげてくださった。
宮越屋珈琲の町田店は、先輩作家や大学教授なども使っていたお店で、店先には常連客の書籍がいくつか並んでいます。チェーン店なのでほかの宮越屋に行くこともありますが、そうした先輩作家のおかげで町田店はとくに物書きに寛容な空気が流れている気がします。お客さんもみんな落ち着いていて、駅前なのに電源やWi-Fiもあって、ほどよく空いているので、重宝していました。
一作目の『明け方の若者たち』も、ほとんどこの店で書いています。2階の喫煙席が好きで、自分は非喫煙者のくせに何故かそこで原稿を書いていました。駅の近くにコワーキングスペースができてからはお店に来る機会も少し減ってしまったのですが、今でも変わらず、好きな店です。
ライターの頃から筆が進まないと「場所」のせいにしがちで、集中できないからとあちこちに移動していました。カフェ・グレは本を読みたいときに使っていて、久美堂の隣のドトールは気取った人が少なくて落ち着いているので、執筆に向いていました。
スターバックスは町田駅近くに複数店舗がありますが、JRと小田急線を繋ぐ道の途中にある「町田パリオ店」を頻繁に利用していました。なぜかチェーン店のほうが仕事に集中できるので、ずっとその辺りを利用していた気がします。あと、ぽっぽ町田店のスターバックスでは、隣に座った人がリュックから大きなモニターを取り出して、その場でNintendo Switchをし始めたことがありました。集中力が完全に切れて、すぐに帰った覚えがあります(笑)。
――なかなかパンチのあるお客さんですよね。
本当におもしろかったです。町田を歩くと、「この人、普段は何してんだろう?」と疑問を抱きたくなるような、得体の知れない人をたまに見かけます。自分自身も、他人から見たらそう思われているかも知れない。この得体の知れなさが、令和のまちとしては重要だと思っています。規定から少しでもはみ出せば何かと排除されがちな時代に、自由でいられる余地がある。そんな町だから、人も集まるのだと思います。
仲見世商店街も、本当にいろんな人がいますよね。店員さんも個性的な人が多いし、若手の店と老舗の店が共存しています。街として欠かせない場所だと思います。
――こういう個人店がたくさん残ってますしね。
ここ数年、行政や大手資本がトップダウンの形でつくる街が増えたな、という印象があり、どれも似たような外観の店をしています。その流れに反抗するように、町田は小さくて古い店が変わらず愛されている。 カレー店の“アサノ”などはとても有名ですが、あんなにわかりづらいところにある店によくみんなたどり着くなあと、行列を見るたび、その愛の大きさに驚かされます。
“アサノ”のように、ある人たちからすれば聖地のような場所が、町田にはいたるところにあります。でも、僕はそこにどっぷり浸かっていたわけではなかったです。どちらかといえば、そういう人たちを羨ましく見ていた。一見さんが入りにくそうな店に悠々と入っていく人たちに憧れる日々でした。
ただ、生活者としては新しいものも古いものも両方あるのがちょうどいい気がするんです。現代社会に適応しすぎた自分は、都市的な機能がないと生きていけないので、それもあって、町田駅まで徒歩で通える範囲に住んでいたのだと思います。
町田駅の近くにいれば大体のものが揃います。わざわざ都心に出向く必要なんてほとんどなかったですし、都心で芹ヶ谷公園みたいな緑豊かな公園にはなかなか出会えません。芹ヶ谷公園は両脇が山になっていて、その谷間にできた公園なんですよね。山があるから自然が生きていて、子どもたちは雑木林をかきわけるように歩いたり、虫を取って遊んだりできる。子どもが未だに昆虫好きなのは、きっとこの時期、たくさん虫を集めていたからだと思っています。引っ越す前は、ザリガニ釣りもよくやっていました。僕も小さな頃にやっていた遊びなので、そういう経験を子どもにさせてあげられるのも、町田のような郊外都市の魅力だと思います。
今年で38歳になりますが、洗練されすぎた街にいると少し疲れてしまうことに気付いたんです。どこか無理してしまうというか、ずっと背伸びした状態になってしまう。未だに渋谷のスクランブル交差点の最前列に立つとテンションが上がるのですが(笑)、ずっとそのテンションで生活するのはさすがに苦しい。東京生まれだけれど、東京に対して疎外感みたいなものがずっとあって、むしろそれを維持している方が心地よかったりするので、改めて町田という選択肢は自分に合っていたと思います。
小説家としての始まりと
海の近くで暮らしながら物をかくということ
――サラリーマンからの転職は、周りの反応はいかがでしたか。
大企業から社員6名の零細企業への転職だったので、誰も賛成してくれなかったです(笑)。賛成派が1人もいない選択なんて珍しいですが、最後まで責任を取れるのは自分しかいないし、あのまま大企業で定年を迎える未来が想像つかなかったので、飛び込んでしまいました。
――小説を書こうと思ったきっかけは?
編集プロダクションに入社して取材記事だけでなくエッセイや短いフィクションなども書かせてもらっているうちに、出版社から“小説もいけるんじゃないか”と声をかけてもらえるようになりました。 5〜6年前までは企業のオウンドメディアも元気で、WEBでいろんな記事を欲しがられた時代でした。インタビューやエッセイだけではつまらないから、何か短い小説みたいなものを書いて、という依頼も多く、3000文字程度の短い物語を書いていたら、“10万文字の物語も書けるんじゃないか”と幻冬舎さんが最初に声をかけてくださったのがきっかけです。

――最初の短い話はどういう話だったんですか。
アルバイトメディアからの依頼で、架空の履歴書を3枚渡されて、その履歴書から3つの物語を作ってください、という内容でした。たまたまそれを読んでくださった出版社の編集さんが声をかけてくれて、最初の小説につながりました。
アルバイトの掌編も、一作目の小説も、調べものはほとんどせずに自分の見てきたものや感じたことを昇華させて書いたものでした。今でも内側から出てくるものと、自分の目に映るものの範囲で物語を書くことは多いです。そういう意味でも、町田は本当にいろんな人が歩いているし、都市的機能も豊かな自然もあるので、ネタにできるものが多くて良かったと思います。
目に映るものから何かを生む以上、住んでいる町の影響は必ず出ます。三年ほど前に海の近くに引っ越したのですが、やはり住環境によって書く内容は変わっていきました。今の生活では出会う生物の数が圧倒的に違うし、リモートで完結する仕事も増えて、人と会う機会はずいぶん減りました。
より自然が豊かなエリアに引っ越したことは現時点ではプラスに働いていますが、そもそも町田に住んだ時期がなければ、海の近くに住もうとは思わなかった気がします。東京から急に海の近辺に住むのはちょっとジャンプしすぎている気がするし、もっと勇気が必要だったでしょう。町田というワンクッションがあったから、海も行きやすかった。コロナ禍以降、地方への移住が流行っていたことも後押しして、抵抗なく引っ越せたのだと思います。
――定住するみたいな感覚はあるんですか?
昔は定住をダサいことだと思っていたんです。住宅ローンなんてフットワークを重くするだけだし、もっと身軽でいるべきだと考えていました。でも、今は一つの土地に根を張って幹を太くすることのほうが、より大きな価値を感じられます。都心から離れることで流行にいち早く着いていかなきゃいけない! といった焦りから解放されたことも大きいです。物語を書くときは外部の影響を受けずにいるほうが、より深く潜れます。


――ここ数年の社会の状況で、どこに住むかって考えるシーンが色々出たような気がします。
職種が変わるとか、コロナ禍で社会が変わるとか、そういうタイミングで人々の住環境が変わることは自然な流れだと思います。最近は物価も上昇し続けていて、電気代も野菜もなんでも高いですし、本当に生活しづらい状況が続いています。固定費を下げるなら引っ越す必要があるし、収入を増やすなら転職する必要がある。そうした判断を迫られている人は多い気がします。あと僕の場合は、最近のSNSの閉塞感があまりに苦しいので、画面から目を離して、近所を散歩して、遠くで鳴いているトンビの声を聞くとか、そういう時間を必要としていたこともあります。
家の近所では春先から夏前までずっとウグイスが鳴いているのですが、最初のうちはまだ発声が下手だった鳥が、季節が変わる頃にはとても上手くなってくる。その声を仕事場で聞いていて、成長を感じ取れる心の余裕があると、安心できます。切羽詰まっているとウグイスなんかどうでもよくなってしまいますし、海にクラゲが出てきたなとか、とても大きなカニが獲れたなとか、そういう一つ一つの季節の変化に気付かずに過ごしてしまうことはあまりいいことではないと感じています。
――豊かな住環境っていうのがすごく、分かりますね。仕事へちゃんと生かされるという。
小説には風景描写が必要なので、そのバリエーションを増やすためにも今のまちにいる気がします。小説家という仕事に引っ張られて生活していること自体が気持ち悪くもあるんですけど、今はそれに踊らされているぐらいがちょうどいいとも思えます。
仕事が変わると、キャリアは1年目に戻ります。僕はサラリーマンを5年間やっていたのに、転職してライターになったからまた1年目に戻って、それが6年ぐらい続いたところで、今度は小説家として1年目に戻りました。年齢だけは重なっていきますが、気持ちとしては新卒が始まったばかり。勉強ばかりですが、それも楽しんでいますし、この生き方に飽きるまでは、今の暮らしを続けたいと思っています。
PROFILE
1986年 東京都生まれ。サラリーマンからフリーライターへ転身。のちに、小説家として2020年『明け方の若者たち』(幻冬舎刊)でデビュー。翌年にはバンドindigo la Endとのコラボレーション作品として二作目となる小説『夜行秘密』を刊行。2024年、三作目の長編小説を含む3冊の新刊を刊行予定。@katsuse_m
@katsuse_m
*1村山由佳によるライトノベルシリーズ。ジャンプ ジェイ ブックスより1994年9月から2020年6月まで、集英社文庫より1999年6月から2020年6月までそれぞれ刊行された。シリーズ累計部数は550万部を突破。
*2宗田理による日本の小説シリーズ。角川書店より1985年4月から刊行され、徳間書店やポプラ社への移籍を経て、2009年3月からは角川つばさ文庫 より刊行。『ぼくらの七日間戦争』は映像化も多い作品。